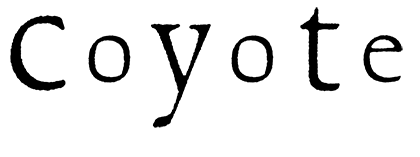角田光代×ピコ・アイヤー×ジェフ・ダイヤー
ジョン・フリーマン(モデレーター)
ジョン・フリーマン(モデレーター)
Mitsuyo Kakuta × Pico Iyer × Geoff Dyer
John Freeman (moderator)
一つの土地から別の土地へ。
旅をすることに魅了され、旅を書いてきた3人の作家たち。
いつも旅の中にいる彼らだから見えること、それは──。
text by Ide Kosuke photograph by Omori Katsumi illustration by Yamaguchi Kayo
旅で気づいた日本らしさ
- フリーマン
- 今回の対談テーマは「現代の旅」。旅と、その教え、歯痒さ、そして歓びについてお聞きしたいのですが、ピコはインド人の両親の元で育ち、アメリカやイギリスに住み、二十代になってから学校へ行きましたね。初めて自分で決めた旅について教えてください。
- アイヤー
- 私は生まれてすぐに、旅が第二の故郷になりました。どこにいても部外者であることが普通だったし、九歳の頃はいつも空港の近くにいました。十七歳の夏は、長いあいだ音信不通だった叔父、叔母と従兄弟を訪ねました。あの頃はいつもボロボロになったレナード・コーエンのカセットテープとアコースティックギターと、インドの成り立ちにまつわる本を持ち歩いていましたね。その後イギリスに戻って高校を卒業し、冬にはカリフォルニアで働き、春になるとバスに乗ってラパス、ボリビア、それからブラジルへ飛んで、南米の東海岸を廻ってマイアミに戻り、グレイハウンドバスに乗りました。大学に進学したのはそれから二カ月後のことでした。
- フリーマン
- 角田さんは初めての旅はどこでしたか。
- 角田
- 私は大学生の頃までツアー旅行をしていたんですけど、大学を出て、初めてバックパッカーとしてタイを旅して、主にアジアを中心にずっと貧乏旅行をしていました。三十代になってからようやくヨーロッパに行くようになりました。
- フリーマン
- ジェフも旅人としてのキャリアはバックパッカーとして?
- ダイヤー
- 私の経験はピコとは正反対でしたね。両親はどこへも行かなかったし、私の家には国際的なことが何一つなかった。第二次世界大戦直後、父はインドへ送られましたが、その後は一切旅行をしなかった。休日でも出かけることなく、子供の頃は父がやる思いつく限りのあらゆる苦痛なアクティビティにつき合わされたものです。母も七十代前半までイギリスを出たことがなかった。二人とも、人生で一度も飛行機に乗ることがなかったなんて驚異的に思えるけれど、そんな「根を張る」という習性が、自分にも素質としてある気がします。デーヴィッド・ハーバート・ローレンスをはじめ、たくさん旅をしている人を知ったのは、大学を出て本を読んだ時でした。私は二十三歳になるまで飛行機に乗ったことがなかった。旅がピコの人生であったように、私の人生は家にいながら節約することだったわけですね。
- フリーマン
- 今まで旅した中で、自分が変われると思った場所はありましたか。
- 角田
- 私は旅行するとますます日本的なものに縛られていくというか。旅行する度に「何でみんなこんなに違うんだろう」と思う。私は本当につい最近まで、「みんなが違っていて私は普通なんだ」と思っていたんですけど、三十年くらい旅行するようになってようやく、いや日本が変わっていて、他の国のほうが普通なのではと思うようになったんです。ただ、そういうことを思っていても「普通」にはなれなくて、どんどん普通の中で怖気づいていて、より日本的な自分になっていくんですね。
- フリーマン
- 旅行中、どんな時に自分の日本人っぽさを感じますか。
- 角田
- 例えば、よその国の方々は、どんな国を旅していてもお互いによく喋るんですね。知らない人同士で声を発するということが、普通にできる。もし一緒にバスを待っていたら、「遅いわね」とか「その服どこで買ったの」と知らない人に話しかけられることがある。バスの順番を間違えていると、「そちらではなくてこちらが先ですよ」などと誰かが声をかけるんですけど、日本だと声を発さない。「念」を送るんです。チラチラっと見て、間違えてますよ」っていう視線を送って(笑)。それで「ああ、順番間違えた」って気づくんですよね。言葉を発することは日常的には少なくて、想いを飛ばして分かち合うことで生きている。外国にいるなら自分もどんどん声を発すればいいんですけど、日本的に黙って、伝わらない念を飛ばしている自分に気づいた時、「こんなに旅してるのに、私はどんどん日本的になっていくな」と、黙りながら思います。
- フリーマン
- それを聞いて、昔彼女とバルセロナのピカソミュージアムに行った時のことを思い出しました。列に並びながらアメリカ人らしく、隣の人と話し始めたんです。それが見知らぬ人と交流することへの抵抗心があるイギリス人の彼女にとって恥ずかしかったようでした。ピコは旅行中、自分の中にある沢山の文化のうち、特にどれかひとつが込み上げてきたという経験はありますか。
- アイヤー
- いつもイギリス文化ですね。私は元来、常にそこから抜け出したい旅人なんです。一九五二年と八二年にイエメンのアデンにいたのですが、何年かして再度訪れると、今まで見た中で一番壊滅した場所になっていました。道もない、店も家もない。メインストリートにはヤギがゆっくり歩いて、たまに車が停まると女性たちがドアや窓を叩いて物乞いする。私がホテルのロビーで座っていると、親切で優雅なホテルマンがやって来て「あなたのフライトが延期になりました。今日は出発できません」と言ったので「どれくらい待つのですか」と訊くと「そんなに長くないです、四日間」だと。アデンでは四日が四年にも四十年にもなるに違いないと思った。その夜イライラしていたら、老人がやって来て切実にお金が欲しいからなのか、誘拐があとをたたない町を車で抜けて、国から出してやると言うんです。どんなバスの運転手が命を危険に晒すでしょうか。私は六時間後に空港に走っていって、朝六時のフライトを見つけて飛び乗った。それはイギリス的だなあと思った。別の時にまたイギリスを感じたことがあって、それは二〇〇一年の八月でした。五週間後、私は母の住むカリフォルニアでどうしたらサンタバーバラとイエメンを同じ文章の中で表現できるのか考えていました。すると母が「世界貿易センタービルに飛行機が突っこんで、みんなお前が最近行った辺鄙な場所について話しているわよ」と言いました。諸悪の根源はイエメンだと、皆が決めたわけですが、私は数カ月前にイエメンで親切な地元民たちに会っていた。私にとってはCNNで観るようなテロリストのはびこる地域ではなかった。私はそう考えられたことに感謝した。おそらくこれもイギリス流の考え方だと思います。