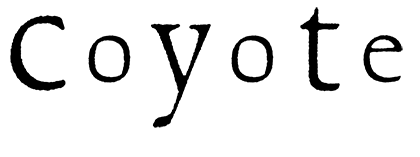もう一つ、文学を通じて国際的な交流が可能になったのには、翻訳という大事な仕事が関係している。文学そのものが権威主義的だった時代、翻訳は仕方なくするものだという見方がされていました。その頃は「シェイクスピアは原文で読まないとわからないよ」と、大学の先生たちは偉そうに言っていたけれど、そんなことを言っていたら、文学はそれぞれの言語の狭いところに閉じ込められてしまう。ほとんどの人は翻訳で世界文学を読むのです。翻訳は文学にとって必須のプロセスです。言ってみれば、二つの言語の結婚から新しい作品が生まれるのです。翻訳という知的操作を経て新しい作品が生まれる。そうやって作品自体が元の著者の手を離れてなお成長していく、という役割を担う大事な、そしてとても楽しい仕事が翻訳であると思います。
我々は二年前、東日本大震災という大きな災害をむかえました。津波は多くの人の命を奪い、原発が壊れて大量の放射性物質が外に漏れました。津波が奪ったのは我々と同じ世代の、同じ時代に生きていた人々の命です。そしてこれから原発が奪うであろうものは、次の世代、未来の人々です。どうすればこの理不尽な、不条理を受け止めることができるのか。あれ以来、我々はずっとそのことを考えています。こんなにたくさんの死者たちをどうすれば悼むことができるか。非常に大きな課題を追うことになった。あれ以来、たくさんの人が考え、なんとか作品にしようとした。そうすれば少しはわかるかもしれない、何か方策が見つかるかもしれない、と。そうして二年が経ちました。まだまだ先は長いです。大きな事件が起こると最初にジャーナリストが動く。それから評論家たちが解釈する。さらにその後で文学者がより広く深く理解するために作品化するんです。そういう過程をこれから先もずっと辿らなければいけないでしょう。東日本大震災についての我々文学者の成果は、今後もまた世界中で共有されるものになりうるでしょう。一つだけこの震災を日本の文学者がどうとらえたか、実例を挙げます。照井翠さんという釜石市の学校の先生が書かれた俳句です。
春の星 こんなに人が 死んだのか
この詩人は夜の空を見上げます。そこにたくさんの星が見える。その一方で詩人は、あの津波で二万人が亡くなったということを知っている。数字は知っているけれど、亡くなった一人一人を知っているわけではない。二万人の死者というのは抽象的で、一人一人の死としてとらえることができない。しかし夜の空を見上げて、あの星がみな死者だとしたら、数えられない数だとわかる。そして夜の星は非常に遠いところで手が届かない。もう手の届かないところに行ってしまったが美しい。そういうことが全部、一句の中に凝縮している。俳句の原理は二つの事象を結びつけることにある。一つは自然界、もう一つは自分の心の中。その二つの間に呼応関係が生まれ、そこから一つの感慨が生じる。照井さんはあの震災の悲劇をこういうふうに表現しました。これからもずっと続けられる営みです。
今回我々が南アフリカ出身のクッツェーさんを迎えられたことは大きな喜びです。クッツェーさんはぼくが非常に尊敬し敬愛する作家で、作品では何かを奪われた人々を書かれることが多い。例としてたとえば、『鉄の時代』を挙げれば、主人公であるミセス・カレンという女性は老いて、ひとりぼっちで、非常に暴力的な社会に暮らしている。そういうところから無力感、戦い、苦悩と思索を通じて、人とはいかなるものか、いかに生きるものであるかを描いている。ぼくはこれほど勇敢な、誠実な主人公に出会ったことがありません。そして、今の世界には何かを奪われた人々がたくさん暮らしている。人として持つべきものを持ち得ない国がある。それもまた世界が共有している一つの課題であり、世界文学が表現すべきものです。ある意味では、今の日本、二年前の震災を経た日本人が強く意識して共有しているものでもあると思います。
| 池澤夏樹 1945年北海道生まれ/75年から3年間ギリシャに滞在。沖縄やフランスに移り住む。『スティル・ライフ』で芥川賞を受賞。個人編集による『世界文学全集』全30巻を河出書房新社より刊行。震災から半年後にエッセイ『春を恨んだりはしない──震災をめぐって考えたこと』を発表。近著に『双頭の船』がある。 |