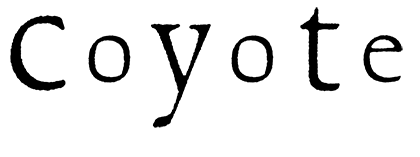その1<東行のうどん>
柴田元幸(翻訳家)

生まれてから50年くらいのあいだ、僕はうどんが好きではなかった。積極的に嫌いというほどではないが、同じ和麺なら、そばの方がずっと好きだった。なぜかと問われれば、(1)食道の末端が極端に細いので細い麺の方が通りやすい、(2)そば粉を使ったそばの方がうどん粉を使ったうどんより栄養的にも豊かである、(3)そばなら「そば湯」でシメられるが「うどん湯」じゃ話にならない、とリクツを列挙することはできたけど、要するに「とりたてて美味しいとも思えない」ということに尽きた。
それが50歳を越したあたりで、『東行』のうどんに出会った。そして、話はコロッと変わった。『東行』のうどんが、細い食道にも優しい細いうどんだったかというと、NO!こんなに太いうどんは見たことがない! 僕なんか一本ずつ、もぐもぐもぐもぐ嚙まないといけない。が、とにかく美味いのである。麺も美味いし、しっかりだしをとったつゆも美味い。ほうれん草や油揚げなどのシンプルな具も美味い。美味ければ、うどん一般に対する上記(1)(2)(3)のごとき不満はいっぺんにどうでもよくなってしまうのであった。
店内はつねにレゲエがかかっていて、僕はレゲエが特に好きというわけではないが、ボブ・マーリー&ウェイラーズの『ライヴ!』を名盤だと思うくらいには好きだし、古風な蕎麦屋でよく聞くテレビの音や今風の蕎麦屋でよく聞く小洒落たジャズなんかよりずっとよかった。店を一人でやっている中田さんは、黙々と一品一品ていねいに作る物静かな、だがどこかにレゲエの躍動感を秘めた職人肌で、店内はすこぶる快適な空間であった(禁煙というのも有難かった)。
そのうちに、まとまった人数で行くことをあらかじめ伝えておくと、メニューにない特別コースを用意してもらえるようになった。以後は、本が出来たときの打ち上げなどに、「うちの近所のうどん屋さんでやりましょう」と主張するようになり、半信半疑でやって来る編集者たちも、出てくる料理一品一品に感心し、もう腹一杯かと思えた時点で出てくるうどんに狂喜するのであった。
『東行』ははじめ僕の自宅から歩いていける距離にあって、海外から帰ってきて自宅に戻るより前に店へ直行したときなど、うどんをもぐもぐ嚙みながら、こういう場が近所にあることの幸福をしみじみ味わった。のちによりよい立地条件を求めて隣の隣の町に移っていった際は、当初はドジャースがニューヨークを去ったときにポール・オースターが受けたのに劣らぬショックを受けたが、じきに電動アシスト自転車を購入してそれも克服した。
諸般の都合で『東行』は目下休業中で、今日はどこへお昼を食べに行こうかな、と考えるたびに『東行』を選択肢に入れられないことを寂しく思う。ボブ・マーリーの『ライヴ!』も、うどんが食べたくなってしまうのでとんと聞かなくなった。でもまたいつか、レゲエを聴きながらあの太い太いうどんが食べられる日が来ると信じている。
それが50歳を越したあたりで、『東行』のうどんに出会った。そして、話はコロッと変わった。『東行』のうどんが、細い食道にも優しい細いうどんだったかというと、NO!こんなに太いうどんは見たことがない! 僕なんか一本ずつ、もぐもぐもぐもぐ嚙まないといけない。が、とにかく美味いのである。麺も美味いし、しっかりだしをとったつゆも美味い。ほうれん草や油揚げなどのシンプルな具も美味い。美味ければ、うどん一般に対する上記(1)(2)(3)のごとき不満はいっぺんにどうでもよくなってしまうのであった。
店内はつねにレゲエがかかっていて、僕はレゲエが特に好きというわけではないが、ボブ・マーリー&ウェイラーズの『ライヴ!』を名盤だと思うくらいには好きだし、古風な蕎麦屋でよく聞くテレビの音や今風の蕎麦屋でよく聞く小洒落たジャズなんかよりずっとよかった。店を一人でやっている中田さんは、黙々と一品一品ていねいに作る物静かな、だがどこかにレゲエの躍動感を秘めた職人肌で、店内はすこぶる快適な空間であった(禁煙というのも有難かった)。
そのうちに、まとまった人数で行くことをあらかじめ伝えておくと、メニューにない特別コースを用意してもらえるようになった。以後は、本が出来たときの打ち上げなどに、「うちの近所のうどん屋さんでやりましょう」と主張するようになり、半信半疑でやって来る編集者たちも、出てくる料理一品一品に感心し、もう腹一杯かと思えた時点で出てくるうどんに狂喜するのであった。
『東行』ははじめ僕の自宅から歩いていける距離にあって、海外から帰ってきて自宅に戻るより前に店へ直行したときなど、うどんをもぐもぐ嚙みながら、こういう場が近所にあることの幸福をしみじみ味わった。のちによりよい立地条件を求めて隣の隣の町に移っていった際は、当初はドジャースがニューヨークを去ったときにポール・オースターが受けたのに劣らぬショックを受けたが、じきに電動アシスト自転車を購入してそれも克服した。
諸般の都合で『東行』は目下休業中で、今日はどこへお昼を食べに行こうかな、と考えるたびに『東行』を選択肢に入れられないことを寂しく思う。ボブ・マーリーの『ライヴ!』も、うどんが食べたくなってしまうのでとんと聞かなくなった。でもまたいつか、レゲエを聴きながらあの太い太いうどんが食べられる日が来ると信じている。
柴田元幸 翻訳家。文芸誌MONKEYの責任編集を務める。
最近の訳書にポール・オースター『写字室の旅』、ブライアン・エヴンソン『遁走状態』がある。