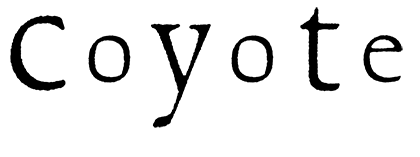text and photograph by Kataoka Yoshio
夏のための新作として、パタゴニアがその年の夏の初めに発売した、何点かの半袖シャツのうち、5枚を僕は買った。梅雨明けの前後だったと思う。買った次の日、梅雨の雨が降る気温の低い日に、5枚のうちの1枚を僕は着て歩いた。5枚あればひと夏は大丈夫かな、と僕は思った。
お盆を過ぎたばかりの頃になると、5枚の半袖シャツに僕はすっかりなじんでいた。体がなじんだだけではなく、気持ちまでが、5枚の半袖シャツになりきってしまった。よく晴れた暑い日の午後、待ち合わせの喫茶店に向けて、僕は下北沢の北口を急ぎ足で歩いていた。
その僕は小さな四つ角を越えたところで、日傘をさした女性に呼びとめられた。年配の、と言っていい、まったく知らない女性だった。歩道のない狭い道の端に寄ったその女性は、「知らないかたをこんなふうにいきなり呼びとめて、いけないことかしらねえ」
と、笑顔で僕に言った。さて、いったいなんの話だろうか、と思いながら僕は彼女の、純粋な笑顔を観察した。
「お召しになっているそのシャツの、色や生地が、懐かしいわねえ。向こうから陽ざしのなかを歩いてらっしゃるのが目にとまったとたん、懐かしくて懐かしくて、昔のことが次々に思い出されて。そのシャツは、ひょっとして、お仕立て直しかしら」
そう言って彼女は、そのとき僕が着ていたパタゴニアの半袖シャツを指さした。お盆を過ぎたばかりの、よく晴れた暑い日の午後の陽ざしが当たっている彼女の指先に視線を向けた次の瞬間、僕の頭のなかに閃いたのは、銘仙、という言葉だった。銘仙とは、女性の着物や布団などに使う、絹の織物だ。染色した玉糸を平織にして出来る布地だ。
銘仙、という言葉が閃いた瞬間、僕にとっても謎のひとつが氷解していた。夏の初めに買ったパタゴニアの半袖シャツ5枚のうち、これまでの日本語だと茶色としか言いようのないかなりのところまで複雑な色と作りの生地を使った1枚に対して、着るたびにふと感じた、ごく淡い懐かしさあるいは親近感、さもなければごく軽い既視感のようなものの正体が、はっきりと見えたからだ。
そう、この半袖シャツの生地は、色も構造も、銘仙の感触なのだ。僕が子供だった頃、日本の女性たちは銘仙の着物を盛んに身につけていた。僕を呼びとめた日傘の女性も、若い頃には銘仙に親しんだはずだ。日常的にあまりにもなじんだ銘仙だったがゆえに、銘仙の感触の生地で作ったパタゴニアの半袖シャツを目にした彼女は、僕を呼びとめずにはいられなかったのだ。
「僕が子供だった頃、母親はこのシャツとよく似た生地の着物を、いつも着ていました」
と、僕は彼女に言った。
「お仕立て直しなの?」
という彼女の問いに、
「いいえ」
と、僕は答えた。
「夏の初めに買った、アメリカ製の既製品です」
という僕の説明に、彼女は驚いていた。
「アメリカ製の」
「はい」
僕は自分が着ている半袖シャツの裾をつまんで前へ引っぱり、布地を彼女に触ってもらった。
「まるで銘仙よ」
と、彼女は言った。
「着ていると僕も懐かしい気持ちになります」
「ほんとにそうよねえ」
と、日傘を傾けて彼女は言い、僕たちはそこで別れた。