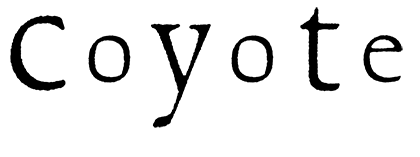この日の半袖シャツとともに、他の4枚が、いまでも僕のところにある。クロゼットのなかを探してみたら、5枚をひとつのハンガーに重ね、ウィンド・ブレーカーの隣に掛けてあった。
梅雨の晴れ間の直射光のなかで、パタゴニアの半袖シャツ5枚の記念写真を僕は撮ってみた。半袖シャツは被写体として面白いと僕は思う。ごくおおまかに言って、着ていたその人の過去が、半袖シャツのふとしたディテールのなかに、ひそんでいる。左の胸にひとつだけあるポケットは、過去そのものだ。5枚の半袖シャツの、それぞれに左胸にひとつだけあるポケットに、僕はいったいなにを入れて、夏のなかのどこを、どのように歩いたのか。まるで新品のようなたたずまいの胸ポケットから、過去を引っぱり出すような写真を撮るのは、至難の技だ。
このポケットの大きさは、縫い代を含めたポケットそのものぜんたいを計って、横幅が15センチ、そして深さは16センチだということを、ついさきほど僕は知った。モレスキンから発売されている、薄いシリーズの手帳が、1本のボールペンとともに、このポケットにぴったりと入るではないか。半袖シャツのポケットが持っている過去とは、そのポケットに入れられていた手帳に記入された、さまざまなことだ。横幅の中央、そして上の縁から2センチ下がったところに、ボタン・ホールが真横に切ってある。本体にひとつ取り付けてあるボタンを、このボタン・ホールに留める。外出するときこの胸ポケットに、スイカを1枚だけ入れておく男を、僕は想像する。彼は胸ポケットにスイカを入れたのち、ひとつだけあるボタンを留める。駅の改札口を入るとき、改札口に向けて歩きながら彼は胸ポケットのボタンを、おそらく右手の指先ではずす。そしてスイカを取り出して改札を入ると、すぐにスイカをポケットに戻し、ボタンをかける。この動作が、ひと夏、ふた夏、さらに次の夏と、連続しただけの過去を持つ胸ポケットというものについて、僕は想像をめぐらせる。何年か前のパタゴニアの半袖シャツの胸ポケットは、そのサイズが横15センチに縦16センチ。さまざまな過去がこのスペースのなかにいまもある。しかもそのスペースは、本体の布地にポケットの布地を、両者ともに平らに縫いつけて、出来たものだ。
パタゴニア、という現実に存在する地名を初めて知ったのは、ずっと以前、子供の頃のことだ。響きはとてもいい。英文字による字面は素晴らしい。僕にとってパタゴニアは、長いあいだこのままだった。そこにいくつかのイメージを強烈に埋め込んでくれたのは、写真家の佐藤秀明さんだ。
夜中に、都会の音などなにひとつ聴こえない、絶対静粛と言っていい静かな空間の彼方から、氷河の割れる音が伝わって来る、というイメージ。海に向けて突き出した氷河が、ついに割れきって海へと落下していくときの、途方もなく底の深い音のイメージ。そしてこの音も、夜のなかを伝わって来る。遠いのかそれとも思いのほかに近いのか、距離の感覚のつかみにくい音、というイメージ。風のイメージも僕の記憶に刻まれて、いまもそこにそのままある。パタゴニアではほとんどいつも、強い風が吹いている。外を歩く人たちは、その風に向かって、四十度近くまで傾いて歩く、というイメージ。鮪漁船に乗り組んでいて怪我をし、パタゴニアで船を降りて治療していた途中の漁船員が、町で佐藤さんを見かけて日本人だと直感したからだろう、自分を必死で指さし、マドロス、マドロス、と何度も言った、というイメージ。自分が船乗りだということを、そのことを伝え得る、そして自分が知っている、唯一の言葉を佐藤さんに放ったのだ。それまでの僕にとって、マドロスは昔の歌謡曲のなかの主人公だったが、佐藤さんからこの話を聞いてからは、僕の知っているマドロスはパタゴニアにいる。