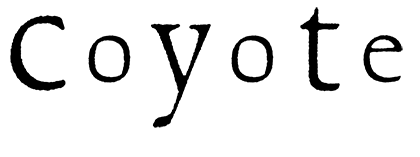「ノースショアのいい思い出をさっきから考えているんだ」マークが言った。
「思い出して」ケイティが言う。
「本格的にサーフィンを始めたのは高校の頃だった。サーファーたちは海からあがってくると優しい眼をして”Give me five”と言って片手を叩きあい、感動を分かち合って帰る。それだけで幸せな気持ちになるんだ。特にパイプラインの波の美しさ、あんなに長く乗れるチューブは他にはない。いい波乗りができた日は気持ちが変わる。嵐の中パイプラインの波に乗ると、自分だけの世界で誰にも邪魔されない」
マークはできるだけ長く乗ることを心がける、一つひとつの波が貴重だからと言う。カットバックしてスープに乗って岸まで戻り、少しの時間ラインナップから離れる。そうすれば他のサーファーにもチャンスが巡ってくる。チューブに乗ってすぐにショルダーからプルアウトして次の波というのは彼の趣味ではない。
「素潜りが好き」とケイティは言う。「素潜りはリーフの状態、波、砂、海の中の生活を垣間みることができる。海上に出るとダイヤモンドヘッドも見える。幸せを感じる風景だわ」
マークはフィンを指差して言った。「どれだけの波がこれらを運んだと思う?一つひとつに物語がある。本当にものすごい物語が海の底にあるんだ」
「海の底に残されたアート作品ですね」
「フィンなしではサーフィンをすることはできない。フィンでコントロールをするからね。集めたフィンを見ながら私はこう思うんだ。君らはどれだけの人を幸せにして来たことか……。私たちがサーフをして楽しんでいる時に、自然はたくさんの物を吸収しているんだ」
集めたこれらのフィンの物語を書いてほしいと願った。
「いつかね、そう、それぞれに素晴らしい物語があるからね」
最後に写真を1枚と言うと、太った女王様をカウチの傍らに寄せた。マークはそっと「モップ代わりになり家をクリーンナップする」と笑った。マークとケイティ、二人と1匹の太った猫、それはまるでクリマスカードの絵のように幸せな世界だった。
「『もし家が火事になって一番大切な物をもって逃げるとしたら?』っていう質問をしてくれないか!」マークが言った。不思議な表情をケイティは浮かべてマークの顔を覗き込んだ。
マークは彼女を抱きしめて自らの質問にこう答えた。「一番大切なものは彼女。この女性!こんな私と我慢して海に行ってくれる」
高台の家まで、長い坂道を運転してようやく辿り着く。でもこの景色があると思うとその道程も辛くない。朝起きた時の鳥の美しい囀りが森を渡る。