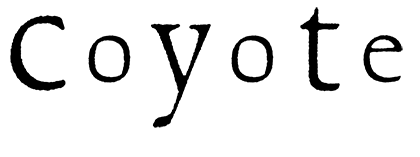文/新井敏記
text by Arai Toshinori
写真/佐藤秀明、新井敏記
photography by Sato Hideaki, Arai Toshinori
標高232メートルのダイヤモンドヘッドを眼下におさめ、海に沈む太陽をゆっくりと眺める彼らの家のテラスは広々として、バミリヤやパパイヤの木が実をつけた亜熱帯植物がテラスを囲み、ブーゲンビリアやショウガ科の彩り豊かな花を咲かせている。イギリスの水夫が火口から見つけた方解石の結晶をダイヤモンドと間違えたことに由来するダイヤモンドヘッドを、ハワイの先住民は「レアヒ(マグロの額)」と呼んでいたが、なるほど遠くここから眺めるとまさにレアヒと呼びたくなるような姿だった。
夕方近く月は真上にあった。
「今日の夜は満月、でも少しおぼろだから明日は天気が悪くなる」
ケイティが白道の軌跡を指で描いていった。彼女はマークの腕を両手で抱いて甘える仕草を見せた。
部屋の装飾はケイティのセンスだった。目を引くのはまずリビング中央に置かれた大きなカウチ。クッションにはそれぞれ異なる刺繍が施されており、見る者を楽しませる。中央に座した猫が客人を無視するようにでんと構えている。
ケイティが「猫がこの家の女王様なのよ」と笑った。
「ここに来てもう10年になる。たぶん6時から日が沈みはじめて、とても綺麗な光が見える」
マークが言う。「ケイティと知りあったのは9年前、ある友達の家のディナーパーティで再会したのがきっかけだったね」
「6月1日、2人とも結婚していた」ケイティが答えた。「彼が丁度ライフガードを引退した頃、私も宝石のデザインを始めた頃だった。いっしょに旅をしたりして、いいタイミングだった」